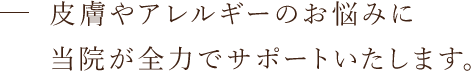とびひ(伝染性膿痂疹)について
4月に入り、新生活をスタートされた方も多いかと思います🌸
環境変化で体調は崩されていませんか?😄
コロナウィルスまん延の関係で、うまくスタートを切れなかったとお話しされる患者様もいらっしゃいます💦
まだまだストレスフルな環境ですが、上手にリラックスタイムを設けながら乗り切りましょう❢
さて本日は、夏にかけて流行が増える「とびひ」についてご説明致します。
☆とびひ(伝染性膿痂疹)とは?
虫刺され、汗疹、湿疹の掻き壊しなど、ささいな傷から菌が入り感染して起こる皮膚感染症です。
☆原因
夏に多い疾患で、主に子供に多いです。
黄色ブドウ球菌、またはレンサ球菌による感染で、その産生する毒素により水ぶくれ(水疱)や膿(膿疱)ができます。
同時に痒みが生じるため、それを掻きむしり次々に周辺に水疱が生じ広がります。
☆症状
とびひには、水疱ができるタイプと瘡蓋(かさぶた)ができるタイプがあります。
・水ぶくれタイプ
→ 赤み、痒みを伴う水疱ができ、その水疱を触った手で別の部位を触ることで、あちこちに広がっていきます。
・瘡蓋タイプ
→ 赤みから膿疱ができ、それが破れて厚い瘡蓋ができます。
✎その他、発熱、リンパの腫れ等が出る場合もあります。

☆治療
原因となる細菌を退治するための抗生物質の内服、外用、痒みがある場合は抗アレルギー薬をを処方します。
石鹸やボディソープで洗いよく洗い流し、石鹸分が残らないようにしっかりシャワーで流しましょう❢
また患部を触ると感染を広げてしまうため、なるべくガーゼで覆います。
※消毒液は再生しかかった正常な皮膚細胞もやっつけてしまうため、使用しないようご注意下さい♪
洗うことが大切です😄
☆予防
・お風呂に入り、石鹸で良く洗い、肌を清潔に保つ
・爪を短く切る
・外出や遊んだ後は、手を洗うようにする
🌟感染症のため、症状が広がる前に早めの治療が大切です✧˖°
「もしかしたら・・・」と思ったらお早めにご相談下さいね(^-^)
タコとウオノメについて
春の陽気が感じられる季節になってきましたね。
本日はタコ(胼胝)とウオノメ(鶏眼)についてご説明致します。
🌸原因
どちらも手足の一定の部位に摩擦や圧迫が繰り返し加わることで、皮膚の角質が厚くなることでできます。
繰り返される刺激に対する皮膚の防御反応とも言われています。
刺激の原因には…
・足に合わない窮屈な靴を履く
・革靴やハイヒールなど底の固い靴を履く
・足の変形や歩き方
・長時間の歩行や立ち仕事
これらが関係しています。
🌸症状
【タコ】
ウオノメより大きめで、周囲の皮膚が黄色味を帯びています。
扁平であることが多く、圧迫しても痛みは少ない。
足裏やくるぶし、足の指・手指などにできやすいのが特徴です。
【ウオノメ】
大きさは小さいが円形に皮膚が硬くなり、中心に白っぽい芯があります。
圧迫すると強い痛みがあります。
足裏や足指・足の間などにできやすいのが特徴です。
※ウイルス性のイボも症状が似ている為、鑑別が必要になります。

🌸治療と予防
皮膚が厚く、固くなっている部分を専用の器具で削る処置をします。
削りの処置で痛みを抑えることが出来ます。
市販のスピール膏や鶏眼パットを貼ってトラブルを引き起こす場合もあります。
痛みが強くなる前に受診しましょう❢
タコ・ウオノメは難治性の為、定期的に病院を受診しましょうね😄
また足にあった靴を履き、そこの柔らかい靴を選ぶのもポイントです♬
気になる症状がある方はお早めにご相談くださいね(*^-^*)
2020/03/16新型コロナウイルス感染症対策ご協力のお願い
新型コロナウイルスによる肺炎が国内で発生している現状を踏まえ、感染拡大防止のため以下の様に患者様にご協力をお願い致します。
🌸咳や鼻水など風邪様症状がある患者様は、受診時になるべくマスクの着用をお願い致します。
🌸下記に該当する患者様は、恐れ入りますが受診前に電話相談窓口のいずれかへご連絡下さい。
・37.5度以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
◇東京都福祉保健局 帰国者・感染者電話相談センター
‣ 池袋保健所:03-3987-4179(9時~17時)
‣ 練馬区保健所:03-5984-4761(9時~17時)
‣ 板橋区保健所:03-3579-2321(8時30分~17時)
◇東京都福祉保健局 新型コロナウイルス感染症相談窓口
電話番号:03-5320-4509
対応時間:9時~21時(土日祝日を含む)
対応内容:感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応など、新型コロナウイルス感染症に関するご相談
✎最寄りの保健所でも対応しております。
◇厚生労働省 電話相談窓口
電話番号:0120-565653
対応時間:9時~21時(土日祝日を含む)
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
2020/02/25巻き爪・陥入爪について
2月も終わりに近づき、梅の花が咲き始め春の気配がしてきましたね🌸
花粉症のお悩みで受診される方も増えてまいりました。
花粉による皮膚炎はもちろん、飲み薬や目薬、点鼻薬の処方もできますのでいつでもお越しくださいね♫
さて、本日はこれから迎えるサンダルを履く季節に向けて「巻き爪・陥入爪」についてご紹介致します。
🌷巻き爪・陥入爪とは?
足の爪の角が周囲の皮膚に刺さり、赤みや痛みが生じ炎症が起こる状態をいいます。
細菌感染を引き起こすと化膿したり、そのまま放置をすると肉芽組織(赤く柔らかい、盛り上がった粒上の塊)が形成されてしまう場合もあります。
🌷原因
‣ 先の細い靴や長時間の立ち仕事により、爪が外側から圧迫されて生じる
‣ 深爪
‣ 誤った爪の切り方(端を無理やり切ることで棘状なって残り、皮膚に食い込み痛みや炎症を伴う)

🌷治療法
‣ 爪を伸ばし、正しく切る
→ 爪の端が指の外に出るまで伸ばし、角は切らずに四角く切りましょう。
‣ アンカーテーピング
→ 皮膚にテーピング材を固定し螺旋状に巻き付け引っ張ることで、食い込みを抑える方法です。
‣ コットンパッキング
→ 爪の食い込み部分に綿を詰め、爪を持ち上げる方法です。
‣ ネイルアイロン
→ 爪はタンパク質のため、熱を加えることによって変形します。
それを利用し、火で熱した専用の鉗子で爪を持ち上げる方法です。
‣ 抗生剤の外用、内服
→ 尖った爪が皮膚に食い込み、細菌感染を引き起こしている場合は抗生剤で治療します。
‣ 液体窒素による冷凍凝固術
→ 肉芽腫を生じている場合の治療法となります。
‣ フェノール法
→ 難治性の炎症を伴う陥入爪に対する手術療法(局所麻酔)です。
🌟症状によって治療法が異なります。
軽度のものは爪の切り方を変えるだけで症状が和らぐ可能性があるため、お早めにご相談下さいね😄
また、ご自分で爪を切るのが難しかったり、切り方がご心配な方は当院で爪切りも行っております♫
「爪切りだけで受診していいの?」と喜んでくださる方が大変多いため、気軽にお声掛けくださいね(*^-^*)
しもやけについて
春が近いて来ましたが、まだまだ底冷えする毎日が続きますね。
今回は「しもやけ」についてご紹介します。
しもやけは、冬の寒さなどによって血行が悪くなることが原因で起こります。
特に手足など末梢の血管では血行のコントロールがしにくくなり、赤く腫れたり、かゆくなったりという症状が起こります。
1日の気温差が10度以上になると起こりやすく、真冬よりも晩秋から冬の初め、冬の終わりから春先にかけてなど、寒暖差の大きい季節に多くみられます。
🌸症状
・手や足の指、耳の外側部分のほか、鼻先、頬などが赤紫色~黒っぽい紫色になって腫れます。
・かゆい、痛い(じんじんするような痛がゆさ)といった症状を伴います。
・入浴したり、就寝時に布団に入るなどして体が温まるとかゆみが強くなります。
・悪化すると水ぶくれができたり、さらにそれが破れてジュクジュクした潰瘍になったりすることもあります。

🌸治療法
・血行障害を改善させるビタミンEが配合された塗り薬や飲み薬
・炎症やかゆみが強い場合は、ステロイドの入った塗り薬やかゆみ止めの飲み薬
🌸予防法
・寒冷刺激を避け、保温に努めることが大切です。
特に外出時には手袋や厚手のくつ下、耳あてなどを着用してしっかりと保温しましょう。
・濡れた手袋やくつ下は早めに取り変えましょう。
靴もよく乾燥させるようにしましょう。
・患部の血行を良くするために、その部位をほぐすようにマッサージするのも効果的です。
🌟放置すると重症化してしまい、なかなか治らないこともありますので早めに受診しましょうね😄
2020/02/10花粉の症状と今年の花粉情報について🌸
今年も花粉の季節がやってきましたね🌳
今年も“花粉飛散予測”が日本気象協会から発表されました。
東京の花粉飛散のピークは2月下旬から3月下旬と例年より長くなりそうです。
花粉の飛散量は前年よりも少ないと予測されています。
🌸花粉症の原因
花粉症は、スギなどの花粉(抗原)が原因となって起こるアレルギー疾患の一つです。
日本では、スギのほかにもヒノキ・イネ・ブタクサ・ヨモギなど約50種類の植物が花粉症を引き起こすとされています。
特に春先になると、スギやヒノキによる花粉症の症状が多くなります。
🌸主な症状
・連続したくしゃみ
・サラサラとした鼻水
・涙が出て強い痒み・充血が起こる
それ以外に頭痛や喉の痒みなどの症状があります。
※風邪の症状に似ているため判断が難しい場合があります。
気になる症状があればお早めにご来院くださいね♪

🌸治療について
【内服】くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどを軽くするお薬を処方します。
【点鼻薬・点眼薬】目や鼻に直接使用するため即効性があります。
※花粉の症状が出る前から内服していると、シーズン中の症状を軽減できます。
早めの対策が大切ですよ(^-^)
🌸日常生活の注意点
・外に干した洗濯物は花粉を落としましょう。
・花粉が多い日はなるべく窓を閉めておきましょう。
・帰宅後はうがいや手洗いを心掛けましょう。
・外出時にはマスクや眼鏡の着用をしましょう。
2020/01/27
冬場に気を付けよう!低温やけどについて
明けましておめでとうございます🎍
本年もスタッフ一同、患者様に寄り添った医療と看護を提供できるよう、元気に笑顔で努めてまいります❢
変わらず本年もどうぞ宜しくお願い致します😄
さて、年始6日から診療開始しておりますが、初日から低温やけどで受診される患者様が増えてまいりました。
そこで今回は、「低温やけど」についてご紹介致します♬
🍊低温やけどってなに?
熱湯や油、アイロンなどの熱による皮膚や粘膜の損傷で、熱源の温度と接触時間に応じて損傷が生じます。
特に体温以上60度以下の熱によって起こるやけどを「低温やけど」といいます。
低い温度でも、長時間の接触と圧迫による循環障害が加わった状態でもやけどを生じます。
一見軽いものと思われがちですが、じわじわと進行し深部にまで及ぶケースもあるため注意が必要です。
✎44~51度までの範囲では、温度が1度上昇するごとに低温やけどになるまでの時間が半分になるといわれています。
44度では6時間、45度では3時間で低温やけどになる可能性があります😩
🍊原因
・電気毛布、電気カーペット
・こたつ
・ファンヒーター
・湯たんぽ、使い捨てカイロ 等
🍊主な症状
はじめのうちは痛みは弱く、後からじわじわ痛みを感じるようになり、軽度の赤みと水ぶくれ(水疱)を生じます。
受傷してから1~2週間の間に皮膚の色は白みを帯び、さらに灰白色や黄色っぽい色に変化します。
ひどいものですと、黒色に変化し壊死組織が付いた皮膚潰瘍になる場合や感染を引き起こす場合があります。

🍊応急処置
流水で20~30分しっかり冷やし、清潔なガーゼで優しく覆います。(痛みの軽減、やけどの進行を遅らせる)
衣服に覆われている部分をやけどした場合は無理に脱ごうとはせず、衣服の上から水をかけて冷やしましょう。
水疱は破らず(中の液体成分が傷の治りを助けてくれる)、もし破れてしまったら水疱の殻は剥がさず貼り付けます。
市販の外用薬では症状に適さず悪化する恐れがある為、使用せずになるべく早く受診しましょう。
🍊治療
やけどの範囲や深度によって治療法が異なります。
軽度のものはステロイド外用薬の塗布、大きな水疱がある場合は医師の判断により細い針で穴をあけ内容物を排出します。
傷が深く潰瘍を生じている場合は、その状態に応じて外用薬や抗生剤、鎮痛薬などで治療します。
🌟やけどは受傷してからの時間がカギを握ります❢
痕が残ったり、ケロイドになったりすることがありますので、放置せずに早期に治療しましょうね(*^-^*)
口角炎・口唇炎について
早いもので、今年もまもなく暮れようとしていますね。
年内最後は、「口角炎・口唇炎」についてご紹介致します。
⛄口角炎とは?
上唇と下唇が合わさる唇の両端の口角に赤く炎症が起き、亀裂ができて裂けてしまう症状です。
アトピー性皮膚炎や、ビタミン・鉄分の不足、カンジタ(カビ)感染、口紅やリップクリームによるかぶれ等が原因です。
口を開けた際に皮膚が引っ張られるため、それによっても切れやすくなります。
また乾燥した状態で口を大きく開けることも原因の一つです。
⛄口唇炎とは?
唇がかさかさする、かゆい、ピリピリする、皮がめくれるなど冬場によく見られる症状です。
乾燥による口唇の荒れ、口角炎同様に化粧品などに対するアレルギー反応等が原因です。

⛄治療
・炎症を抑えるステロイドの塗り薬
・カンジタの場合は抗真菌薬
・刺激の少ない保湿剤
・ビタミン剤の内服薬
⛄日常生活での注意点
・大きく口を開ける、舌で舐める、カサブタを剥がす等は悪化の原因となります。
・歯磨き粉や、化粧品などの洗い残しがないか注意しましょう。
・食事が刺激になることもあるため、食べる前に保湿剤を塗り保護しましょう。
・十分な睡眠を取り、バランスの取れた食生活を送りましょう。
🌟市販のリップクリームではなかなか治りづらく、悪化させてしまう場合もあります(>_<)
症状がある場合は早めに受診しましょうね♬
脂漏性皮膚炎について
こんにちは(^-^)
今年も残り1か月を切りましたね。
本日は「脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)」についてご説明していきます。
⛄脂漏性皮膚炎とは?
皮脂腺が多く存在する部位、頭部・顔・脇・胸部などによくできる湿疹です。
皮脂分泌機能の異常やビタミン代謝異常・ストレスなどが原因と言われています。
また真菌の一種であるマラセチアが関与している可能性があるとも言われています。
冬に悪化しやすく、男性に多いのが特徴です。
⛄症状
皮脂分泌の多い頭部や顔面に、フケ様の付着物を伴う湿疹や、薄い痂皮(かさぶた)のようなものを伴う赤みが見られます。
痒みは無いこともありますが、再発・再燃を繰り返しやすいです。
頭皮の脂漏性皮膚炎では、フケ様の付着物が大量に出てしまうこともあります。

⛄治療
基本的にはステイドロの外用が効果的であり、短期間の外用で改善がみられます。
マラセチアの関与も考慮して、カビに効く抗真菌外用薬を使用する場合もあります。
※皮膚の一部を採取して、真菌がいないか顕微鏡検査をする場合があります。
治療薬の使用で一時的に症状が軽快しても、自己判断で薬の使用をやめないようにしましょう❢
治癒する前にやめてしまうと、ほとんどの場合しばらくして再発してしまいます(>_<)
⛄日常生活で気をつけること
・毎日髪を洗い清潔を保ちましょう。
・ストレスや過労は悪化の原因になるため、規則正しい生活を送りましょう。
・ビタミンや食物繊維の多く含まれる食品を取るよう心掛けましょう。
🌟再発・再燃を防ぐために、定期的な診察が大切です❢
脂漏性皮膚炎の方にオススメのボディソープやシャンプーのご案内もしております🧼
特に頭皮はご自分ではなかなか気付きにくいですよね😩
「美容院で指摘された」「最近コートにフケが付着している」など、思い当たる方はお早めにご受診下さいね(*^-^*)
2019/12/09
手湿疹について
11月に入り、秋も本格的になってきましたね
本日は秋、冬に多い「手湿疹」についてご紹介致します。
手湿疹ってなに?
水仕事やパソコン業務をよくしたり、紙幣などをよく扱ったりするために、繰り返し指先に刺激が加わって起こるものです。
特に主婦、美容師、飲食店員などに多く見られる疾患です。
どんな症状?
・皮膚が赤くなり痒みがでる
・小さなブツブツや水ぶくれ、ひび割れができる
・水ぶくれが潰れてジクジクする
・皮膚がボロボロと剥ける
・水や洗剤などがしみて痛い
主な原因
洗剤などの刺激が原因の一つにあげられています。
これで油が良く落ちるように、皮膚表面の脂も落ちてしまい、皮膚の表面がカサカサして荒れてきます。
そのため、刺激を受けやすくなり湿疹が起こってきます。

治療法
・炎症を抑えるためのステロイドの塗り薬
・皮膚を保護するための保湿剤
・かゆみのある場合はかゆみを改善する抗ヒスタミン薬の飲み薬
・ひび割れのある場合はテープ剤の処方
予防法
・水仕事の際は水に直接触れないよう手袋をしましょう。
(ゴム製は刺激になりやすいので綿の手袋の上からゴム手袋をはめると良いです)
・洗剤、シャンプー等は敏感肌用にする。
・保湿剤を1日に何回も使用して手を保護する。
放っておくと悪化しやすい手湿疹(>_<)
少し良くなってきても、再燃しやすい疾患でもあります。
根気強い治療が大切です❢
早めに受診しましょうね(*^^*)